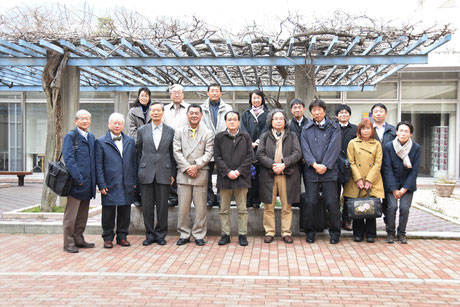3月25日に日本人口学会の関西例会が神戸大学にて開催されました。
今回の例会では北海道から沖縄まで、全国から20名超の参加をえ、盛会となりました。
今回は、近代移行期化に焦点を当て、6つの報告がおこなわれました。たとえば、工業化初期の女工たちの苦しい暮らしと死産率との関連、薩摩藩による琉球での宗旨改の様子など、名もなき人びとがいかに生き、いかに死んでいったのか、その足跡をたどる人口学の魅力が満載でした。
プログラムは以下の通りになります。
プログラム
開会の挨拶:川口 洋(帝塚山大学)
・第1報告
長島雄毅(京都大学・院):職分調査結果にみる明治初期の下京第四区における住民の労働移動
・第2報告(司会:平井晶子)
鈴木 允(横浜国大):大正期における農山村地域からの人口流出の実態―愛知県東加茂郡賀茂村「寄留届綴」の分析から―
・第3報告(司会:高橋美由紀(立正大学))
樋上恵美子(博士(経済学)):周産期死亡率と乳児の先天的な死亡 ―20世紀前半の大阪の母胎の状態―
・第4報告(司会:高橋美由紀)
森本一彦(高野山大学):近世における先祖祭祀と家
・第5報告(司会:中澤 港(神戸大学))
廣嶋清志(島根大学・名誉教授):石見・出雲の人口にみる近代への移行
・第6報告(司会:中澤 港)
溝口常俊(名古屋大学・名誉教授):寺院資料に見る災害列島日本
・特別講演(座長:鬼頭宏(静岡県立大学学長))
金城 善(元糸満市立中央図書館長):琉球・沖縄における人口調査と戸籍資料
閉会の挨拶:川口 洋